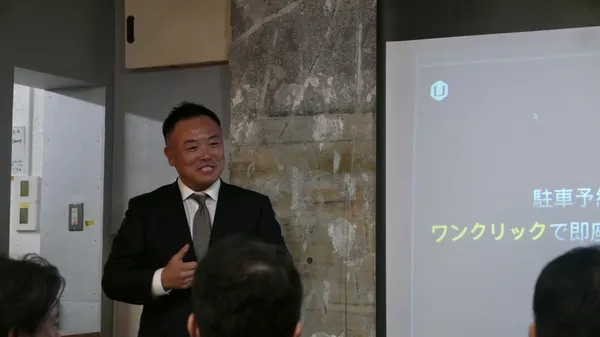一年前、台湾のスマートパーキングスタートアップUSPACEは、大株主である台灣大哥大の支援を得て、日本第三位の駐車場ブランド「軒先」を買収した。1年後、この海を越えた提携の成果が明らかになった。日本市場の収益は前年比115%増を達成しただけでなく、新たに設置した東京・六本木のモデル拠点では、1台あたりの収益性が台湾の繁華街の5倍以上を記録。モデル拠点の収益は3ヶ月で倍増し、単一拠点で月間1,500万円(約300万台湾ドル)を超える収益を上げるという記録を打ち立てた。
この海を越えた提携の成功の秘訣は、USPACEが当初最も誇っていたIoTスマート駐輪場ではなく、現地事情に合わせた戦略転換にあった。USPACE創業者兼CEOの宋捷仁氏は、初期の市場模索を経て、AIナンバープレート認識こそが日本市場を開拓する切り札だとチームが気づいたと明かす。
この1年間、彼らはこの技術をどう活用し、売上倍増の目標を段階的に達成し、日本の競合企業akippaを敵から盟友へと変え、さらに日本の新興不動産企業Post Lintelと三者連合を構築したのか?
日本進出の衝撃:場所取りの習慣がない!
USPACEが軒先を買収した後、最初の課題は台湾のスマート化経験を、構造が複雑で文化的に独特な日本の駐車場環境にどう導入するかだった。
日本市場に初めて進出したUSPACEは、すぐに「ローカライゼーション」の厳しい現実を痛感した。「台湾式の駐車用ロックを日本に押し通そうとしても、絶対に通用しないことにすぐに気づきました」とCEOの宋捷仁氏は率直に語る。台湾では「良い場所を確保する」習慣があり、駐車用ロックを設置して駐車スペースを確保してから車を停めるが、日本ではドライバーは普段から事前に予約して駐車することに慣れていない。
この一見些細な文化の違いが、成否を分ける鍵となった。
「最初は本当に大変でした」と宋氏は振り返る。USPACEは日本に会員基盤が全くなく、設備を設置しても全く利用されなかった。彼は苦笑しながら「私を含め全員が街頭でチラシを配り、アプリをダウンロードしてもらおうとしました」と語る。創業期の原始的な手法に戻ったような日々で、当時は正式なオフィスもなく、Airbnbに詰め込んで設備を組み立てていた。
その後、宋捷仁氏は果断に戦略転換を図った。台湾で誇るIoT駐車ロックを無理に押し付けるのではなく、現地の習慣に合ったAIナンバープレート認識カメラを市場参入の切り札とした。「彼らが慣れ親しんだ『先に駐車する』という習慣から始め、段階的にQRコード決済へ誘導し、最終的に非接触決済を実現した」と彼は語る。日本ではユーザーの習慣を強制的に変えられないと悟り、戦略を迅速に調整したのである。
「日本の駐車文化は正確性と信頼性を重視する。AIナンバープレート認識を導入すれば、既存の施設構造を変更せずにシステムを迅速にアップグレードできるだけでなく、個人データ管理や映像セキュリティに関する現地の厳しい法規制にも適合できる」と、USPACE日本支社の水本真也社長は補足する。この重要な戦略転換が、戦局を逆転させる決め手となった。
三大キーアライアンス:「ユーザーから株主へ」から「敵を味方に」へ、日本市場における三者連合の構築
「AIナンバープレート認識」戦略を確立した後、USPACEは軒先買収による市場地位を基盤に、縦横の連携による包括的展開を推進した。
今年、東京・六本木ヒルズに新拠点を設立した事例がそれを物語る。しかし競争の激しい東京市場で、六本木という象徴的な駐車場を短期間で獲得できた鍵は、巨額の投資ではなく、台湾で始まった不思議な縁にあった。
この縁の始まりは、思いがけない「熱心な会員」に遡る。
その人物こそ、日本第11位の不動産商社Post Lintelの共同創業者、Joey Yang氏だった。宋捷仁氏は笑いながら振り返る。「彼が日本で起業する前から、すでにUSPACEの会員だったんです。奥様は特にヘビーユーザーでした」。
この夫婦はUSPACEが台湾で提供する便利なサービスを非常に気に入っていた。そのため、宋捷仁氏が事業を日本に拡大すると聞いた時、彼らは躊躇なく強い関心を示しただけでなく、不動産専門家としての鋭い洞察力で双方の協力に大きな可能性を見出し、Joey氏が自ら協力の申し出をしたのである。
年齢が近く、起業家同士という共通点から、Post LintelはUSPACE日本法人との提携を自然な流れで実現した。しかしこの関係の本質的な価値は、双方のリソース統合にある。
Post Lintelは日本の不動産分野における深い人脈と専門性を活かし、USPACEにとって最も重要かつ困難な土地資源、すなわち現在六本木の好立地に位置する駐車場の確保を実現。一方USPACEはスマートパーキング技術の導入に注力し、完璧な相乗効果を生み出した。
アプリから始まったこの不思議な縁は、USPACEの日本進出に最も堅固な同盟者をもたらしただけでなく、今後のビジネス展開に向けた新たな扉を開いた。
今後は、日本の大手不動産・管理会社である三菱地所とオフィスビルやホテルなどを統合し、ワンストップのモビリティサービスを展開するほか、USPACEは複数の日本の大手不動産会社や都市再生デベロッパーと戦略的提携を結び、2026年までに日本市場で5,000ヶ所のスマートパーキング拠点を展開する計画だ。これは台湾大哥大Taiwan Mobilityエコシステム初の海外展開成功事例となる。
USPACEが敵を味方に変える:日本シェアリング駐車場業界の「武器供給者」となる方法
USPACEの「クロスドメイン統合」における成果はこれだけではない。最も見事な一手は、市場リーダーであるakippaとの「敵から味方への転換」だが、その戦略は正面衝突ではない。
「私たちが売り込むストーリーは常に同じです。USPACE、軒先、akippaの3社を合わせれば、間違いなくアジア最大規模になります」と宋捷仁氏は語る。
宋捷仁氏は、買収した軒先も市場リーダーのakippaも、この二大共有駐車場プラットフォームの強みは膨大な会員数と駐車スペース数にある一方、共通の弱点はIoTハードウェアを強化する技術能力の欠如にあると指摘した。
そこでUSPACEの役割は、直接参入する運営事業者から、産業を強化する「武器供給者」へと巧みに転換した。「必要な設備やシステムは何ですか?開発して戦いを支えます」。最終的にakippaは提携を選択し、USPACEは無料で駐車場にスマートロックとシステムを導入、その後の駐車収益のみを分配する方式を採用した。
「私の当初の初心に立ち返れば、成功は必ずしも私自身にある必要はない。akippaと軒先がより多くの収益を上げられるよう支援し、私がシステム提供で収益を得ることも、日本市場への進出と同義ではないか?」と宋捷仁氏は語る。この退いて進む戦略は、現地大手との資金力勝負を回避しただけでなく、自社の技術基準を日本の共有駐車場産業の中核に巧妙に浸透させることに成功したのである。
市場展開に加え、AIナンバープレート認識技術で日本市場に参入し足場を固めた後、USPACEは台湾で高度に成熟したスマートモビリティエコシステムを段階的に日本に展開する計画だ。宋捷仁氏は、次に優先的に導入するサービスは空港送迎サービス「UGO」だと指摘する。
「台湾のUSPACEユーザーが桃園空港から最も多く利用する目的地は日本であることが判明しました」。多くの台湾人旅行者からも、この便利なサービスを日本でも利用したいとの要望が寄せられている。宋捷仁氏はこう分析し、これを受けてUSPACEは日本現地のサプライヤーとの提携を進め、台湾ユーザーが慣れ親しんだアプリを通じて直接日本の空港送迎サービスを予約できるようにする方針だ。
上場前の最後の1マイル:「成長」をめぐる10年の長距離走
日本の重モデル買収から東南アジアの軽モデル投資まで、USPACEの海外戦略は一歩一歩が熟慮の末のものだ。
宋捷仁氏は明かす。日本のような高度に成熟しつつも硬直化した市場では、自ら参入し、M&Aと技術統合を通じて決意を示す必要があると。一方、インドネシアやタイなど急成長中の市場では、過去のUberとGrabが東南アジアで繰り広げた補助金戦争のように双方が傷つくより、現地の優秀なチームへの投資を選択する方が賢明だと語る。「競合相手になるより、資金を提供して拡大に専念してもらう方が良い」
こうした一連の海外展開は、より壮大な目標であるIPO上場を指し示している。宋氏は当初の上場予定を2027年第1四半期に延期すると明かし、「ストーリーをより完成度の高い形で伝えたい」と説明。ただし内部監査は完了しており、上場スケジュールにプレッシャーはないと付け加えた。
この上場ストーリーの最も見どころとなる章は、今年12月30日に明らかになる成果となる。USPACEは年末に、移動サブスクリプション制のブラックカードサービス「USPACE Premium」をリリース予定だ。アメリカン・エキスプレス・ブラックカードに対抗するこの最高級サービスは、無料駐車場、空港送迎、代行運転など全ての移動ニーズを統合するだけでなく、ミシュランガイド掲載レストランのグローバル予約など専門サービスへと領域を拡大。同社を単なる駐車場管理から、全方位のスマートモビリティプラットフォームへと進化させることを目指す。
この動きは、USPACEの戦略的焦点が駐車問題の解決からハイエンドユーザー価値の創出へと移行したことを示しており、この戦略的転換を牽引しているのは、宋捷仁氏自身によるこの10年間の深い変革である。
この10年間の起業の旅を振り返り、十分な成功を収めたかと問われると、宋捷仁氏の思考はより根本的な原点に戻った。「もちろん当初の目標より大きく成長した」と認めつつ、「しかし私にとってより重要なのは『成長』だ。成功には様々な定義があるが、成長こそが一生続くものだ。私は決して会社の天井になってはならない」と語った。
この強い危機感と自己要求が、彼を絶え間ない学習と進化へと駆り立てる。生まれつきの輝きなどなく、不断の学びと進化によってのみ、平凡な出発点が遥かなる航路へと向かうのだ。これこそが、上場カウントダウンの中で、この企業が最も注目に値し、かつ最も模倣が難しい中核的資産なのである。